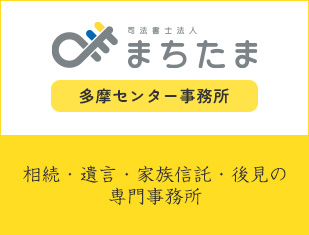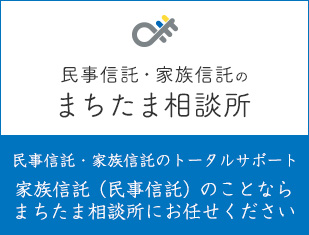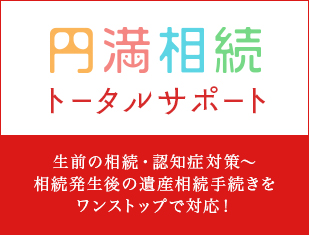信託財産に現金を入れる必要はある?
基本的には現金も信託財産に入れることが望ましいと考えます。
不動産を信託したいのですが金融資産は持っていませんという依頼者の方は珍しくありません。
民事信託・家族信託において、受託者がその信託事務を遂行する上で、信託財産を管理・処分するための諸費用(信託登記費用、不動産の建て替え・修繕費、公租公課等)が生じます。
あらかじめ金銭を信託財産に入れておけば、その中から諸々の費用を支出することができるので、受託者は信託事務をスムーズに進めることが可能です。
しかし、委託者が、信託するほどの金銭を持っていない場合、受託者は信託事務遂行上発生する費用をどこから支払えばいいのでしょうか?
この場合の信託事務の費用について、信託法(48条)では大きく分けて次の2つを想定しています。
① 受託者の固有財産から支払う
→後日、受益者又は信託財産から償還を受ける② 受益者から費用の前払いを受ける
→受益者との合意が必要
②の場合は、受託者は自腹を切らなくていいのでいいですが、①の場合は受託者の自腹です。つまり、まずは受託者が立て替えて、後で受益者又は信託財産から償還を受けるという形です。
信託事務費用を受託者の固有財産から支出した場合について、もう少し細かく見ていきましょう。
受託者の費用償還請求
① 受益者への償還請求
受益者との合意に基づいて、受託者が支出した費用の償還を受けることができます。
但し、あくまで受益者との合意が必要です。
また、信託行為において「受託者は、信託事務の処理に関する費用について、受益者に対して(合意なしに)補償を請求することができる。」などの定めはできないとされています。
これは旧法では認められていたのですが、信託行為の当事者ではない受益者(※)に勝手に負担を強いるのはよくないという意見が多かったため、新法では「受益者の合意」を必要としました。
なお、これについての定めがある信託法48条5項には「別段の定め」を置くことは想定されていないので、受益者の合意を排除することはできないとされています。
※ 信託契約や遺言信託は、受益者の関与なく進めることが可能です。
② 信託財産から償還を受ける
信託財産に金融資産(金銭等)があれば、受託者はそこから支出した分を回収すればいいのですが、信託財産に金融資産がない場合には、受託者は信託財産を換価処分することができるとされています。
但し、当該換価処分をすることによって信託の目的を達成することができなくなる場合には換価処分できません。
不動産信託のみの場合には、不動産を換価処分することは信託目的達成を阻害することになるので、このような場合には信託財産から費用の償還を受けることは難しいでしょう。
信託の終了
受託者が、信託財産から費用の償還を受けようとしたけれど、信託財産では費用の償還に不足している場合、受託者は委託者及び受益者に次の事項を通知し、一定期間を経過しても委託者又は受益者から償還を受けられない時は、受託者は信託を終了させることができます。(信託法52条)
・信託財産が不足しているため費用等の償還を受けることができない旨
・受託者の定める相当な期間内に委託者又は受益者から費用等の償還がされない時は信託を終了させる旨
まとめ
家族信託において、金融資産を信託することは非常に有効です。
そして、個人的にも金融資産は信託するべきだと思います。
しかし、誰もが金融資産を有しているとは限りません。
不動産はあるけど金融資産はない、という方も大勢いらっしゃいます。
ご家族の想い、委託者の想いが家族信託を使えば実現できるのに、「金融資産がないなら家族信託はできません。」とアドバイスすることが専門家として正しいとは思えません。
金融資産がないならないなりの対処法を考えるべきですし、ご家族や親族の協力を仰ぐこと等も考慮して検討することが必要だと思います。
もちろん、無理に家族信託をすることが正解とも思えません。